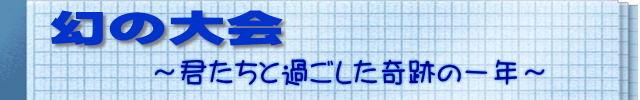
N04 この物語はフィクションで 学校名 個人名 団体名は全て架空のものです。
スマホの方は ブラウザリーダー機能(簡易表示)が見やすいかもしれません。
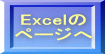
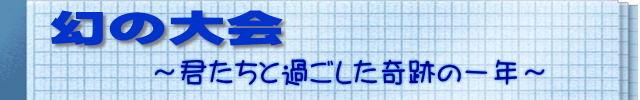 N04 この物語はフィクションで 学校名 個人名 団体名は全て架空のものです。 スマホの方は ブラウザリーダー機能(簡易表示)が見やすいかもしれません。 |
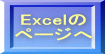 |
N03 N05
中崎真由子は 自分のベッドで泣いていた。説明会の日の晩 家で、
「ねえ、学校でミニバスを今年もすることになったから入っていいでしょ。」と聞いた。
「いいよ。」とあっさり言ってもらえるものだと思っていた親の返事は意外なものだった
「いいけど、3年間やってきたバドミントンはどうするの?どっちもやるのは中途半端だと思うからバスケやるならバトミントンやめなさい。」
父は言った。
「エッ」
小さく呟いた。
「バトミントンはまだダブルスの相手も決まっていないからやめても誰にも迷惑かからないけど、バスケットはチーム競技だし、やりだして今みたいにうまくいかないからって辞めたらチームメイトに迷惑がかかるんだよ。」
やるならそういう覚悟を持ってということだった。しかし真由子にはショックだった。バドミントンもやめたくなかった。というかバスケット自体をやったこともないし一つの競技に絞るというのが小学生にはきつかった。
一晩、泣いては眠り。目が覚めてはまた泣いて眠りにつく。そんなことの繰り返しだった。
バトミントンは3年やってもそんなにうまくならなかった。けどバトミントンもやめたくない。
でも バスケもやりたい。
両方はダメだと親は言う。
学校の友だちの何人かはもうバスケに入って もう練習している。・・・
いつもより早めの起床となった真由子は学校に行く前、母に
「私、決めた。バトミントンやめてバスケットする。お父さんにそう言っといて。」
と言い残して家を出た。
その日。練習開始2日目。真由子は体育館に入るなり、こちらにきて 大きな声で
「中崎真由子です。バスケットをやる決心をしました。よろしくお願いします。」
剛はそんな挨拶をする子なんていなかったのでびっくりしたが、後から思えば真由子なりの決意表明だったのだ。しかし練習を始めてみて思った。
(う~ん、下半身が弱いなあ。それにボールの扱いにも慣れてないなあ。背は高いけどレギュラーの10人に入れるか微妙だなあ。)
最初の二週間足らずで二十数名いた子は20人に減り、勿論毎日20人全員が集まれるわけもなく時には10人いなくて5対5の試合形式の練習さえできない時もあった。そんな中で休まず来ていたのはキャプテンの平島美香、中崎真由子、そして小柄な三井さゆりの三人ぐらいである。
そして、三週間が過ぎた頃、千里中央小学校のコーチ、真島先生から連絡があった。真島先生は2年前まで千里中央小でミニバスケットの指導をされ毎年強いチームを育てることでも有名な先生だ。昨年転勤になり違う小学校にいかれて同じ学校の後輩に指導を譲ったのだがその後輩も転勤になり白羽の矢が元の真島先生に立ったのだ。
「バスケットまたやりだしたんだって?一度、練習試合しないか?」
「冗談やめてくださいよ。うちはまだ部員集めて1か月もたってないんですよ。千里中央小と試合になるわけがないじゃないですか。」
千里中央小のガードとセンターは5年生の時に多くの指導者が見て
「あの子たちは すごい選手だ。」と驚いていた。チーム全体でも来年は大阪のトップクラスになるだろうと認めていたチームである。
「いや・・・、実はこれはお願いなんだ。去年指導者が変わったことで練習日が週2日に減って練習がなくなった日は違う団体が体育館を使うことになった。それで練習場所がないんだ。今年はいいチームだしあのチームも今年でたぶん解散になるだろうから 十分に練習させてあげたいんだ。週2日でも3日でも一緒に合同練習という形で こちらも練習させて欲しいんだ。」
(そういうことか。剛は変に納得した。しかし・・)
「こっちは嬉しいですけど千里中央小学校の子の練習にならないんじゃないですか。」
「大丈夫!どちらの学校にも価値のある練習にするさ。」
真島先生は あっさり言った。
昨年、緑北小が西日本大会にいくことになり、その時はちょうどチームを持っていなかった真島先生に こちらから指導をお願いし、広島にも一緒に行った。その指導方法を、目の当たりにして指導力が素晴らしいことは十分知っている。またその指導を受けることができるなら願ってもないチャンスだ。
「そういうことなら、こちらからもお願いします。」ということで合同練習をすることとなった。
| Copyright(C)2018 furutom |